玉ねぎ栽培において、多くの生産者が直面する課題の一つが「連作障害」です。玉ねぎは連作に強い野菜とされていますが、何年も同じ場所で栽培を続けると、収穫量の減少や品質の低下を招くリスクが高まります。
この記事では、プロの視点から玉ねぎの連作障害に関する正確な知識と、その対策について詳しく解説します。さらに、収益性を高めるための輪作計画として、後作に植えて良い野菜や、逆に避けるべき後作に悪い野菜まで、具体的な品目を挙げてご紹介します。
- 玉ねぎの連作が可能とされる年数の目安
- 連作障害の具体的な症状と原因
- 後作におすすめの野菜と避けるべき野菜
- 土壌改良など効果的な連作対策
玉ねぎの連作障害に関する基本知識
- 玉ねぎは本当に連作可能か
- 連作障害は何年から注意すべきか
- 知っておきたい玉ねぎの連作障害
- 特に注意すべきネギと玉ねぎの連作障害
玉ねぎは本当に連作可能か

玉ねぎは、他の多くの野菜と比較して連作障害が出にくい作物として知られています。そのため、同じ圃場で4〜5年程度であれば、連続して栽培することも一般的です。これは、玉ねぎが特定の土壌養分を極端に消費することが少なく、また根から分泌される物質が他の作物の生育を阻害しにくい特性を持つためです。
しかし、「連作に強い」という言葉を「無制限に連作できる」と解釈するのは危険です。実際には、3年目の栽培で生育不良や収量減に見舞われたという事例も報告されています。土壌の環境や栽培管理の方法によって、連作障害が発生するリスクは変動します。したがって、連作が可能とされる年数はあくまで目安であり、圃場の状態を注意深く観察しながら判断することが重要になります。
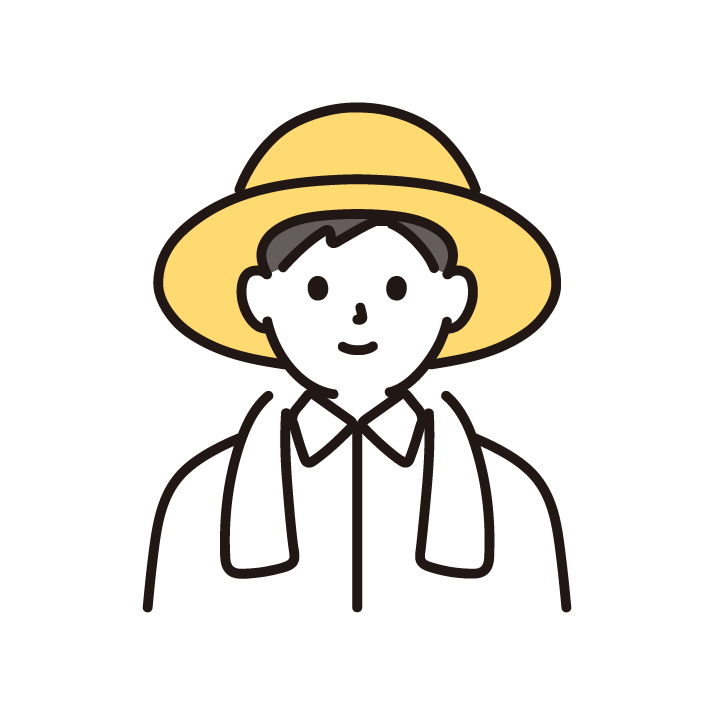
うちは5年やっても大丈夫
という声もあれば、
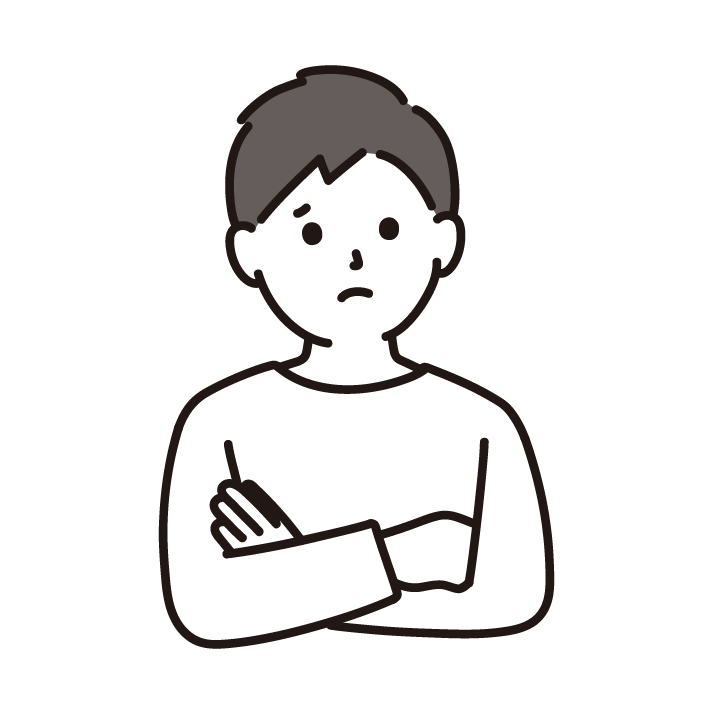
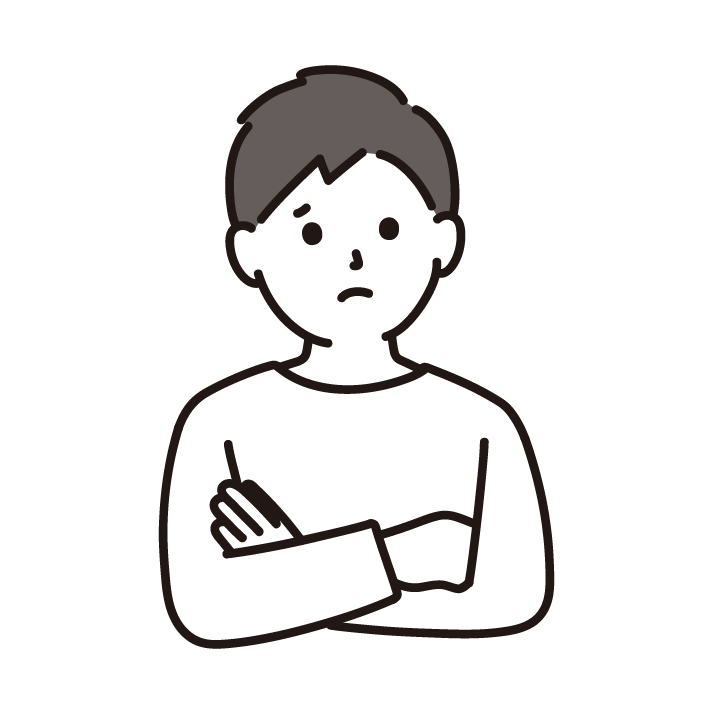
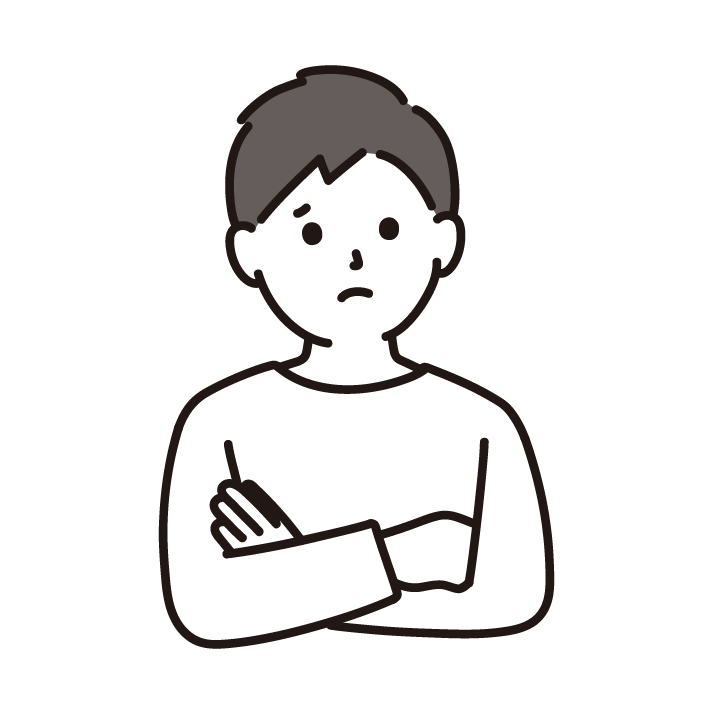
3年でダメになった
という声もあります。
土壌の状態は千差万別なので、ご自身の圃場の状態を把握することが何よりも大切です。
連作障害は何年から注意すべきか


一般的に、玉ねぎの連作で特に注意が必要になるのは3〜4年目以降とされています。最初の1〜2年は問題なく収穫できたとしても、3年目を迎える頃から土壌環境に少しずつ変化が現れ始めます。
この変化の主な理由は、土壌中の微生物のバランスが崩れることにあります。玉ねぎの栽培を繰り返すことで、玉ねぎにとって好ましい微生物が減少し、逆に特定の病原菌や有害な微生物が圃場に定着・増加しやすくなるのです。特に、5年を超えて連作を続けると、収量の低下や病害の発生リスクが顕著に高まる傾向があります。
注意を始めるタイミング
栽培年数だけでなく、前年の収量や品質、病害の発生状況なども重要な判断材料です。もし前年に比べて生育が悪かったり、病気が見られたりした場合は、年数に関わらず輪作を検討することをおすすめします。
知っておきたい玉ねぎの連作障害


玉ねぎの連作障害は、主に3つの原因によって引き起こされます。これらの原因を理解することが、効果的な対策を講じる第一歩となります。
原因1:土壌成分の偏り
同じ作物を育て続けると、その作物が特に必要とする特定の微量要素(マンガン、ホウ素など)が土壌から失われ、欠乏状態になります。一方で、あまり利用されない成分は蓄積し、養分バランスが崩れてしまいます。これは通常の施肥で補う窒素・リン酸・カリウムとは異なる問題であり、生育不良の直接的な原因となります。
原因2:特定の土壌病害虫の増加
玉ねぎを好む病原菌や害虫が、同じ圃場に集まりやすくなります。一度定着すると密度が年々高まり、大きな被害につながります。玉ねぎで特に問題となるのは、軟腐病、乾腐病、紅色根腐病などの土壌病害です。
原因3:植物自身の毒素蓄積(アレロパシー)
植物は、他の植物の生育を抑制する化学物質を根から放出することがあります。これをアレロパシー(他感作用)と呼びます。同じ作物を連作すると、自らが放出した物質によって生育が阻害される「自家中毒」の状態に陥ることがあり、これも連作障害の一因とされています。
これらの原因が複合的に作用し、
- 玉が大きくならない
- 生育途中で枯れてしまう
- 根が少なく腐りやすい
といった症状として現れます。
特に注意すべきネギと玉ねぎの連作障害


玉ねぎ栽培において、輪作計画を立てる上で最も慎重な判断が求められるのが、同じヒガンバナ科(旧ユリ科)に属する、いわば「親戚」のような野菜との関係性です。具体的には、長ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、ワケギといった、ネギの仲間全般がこれに該当します。
これらの野菜を玉ねぎの前後で作付けすることは、単なる連作と同等、あるいはそれ以上にリスクの高い行為と認識しなくてはなりません。その理由は、好む生育環境や必要とする養分が似通っているだけでなく、決定的な問題点として、発生する病害虫がほぼ共通しているからです。これにより、病害虫が圃場に定着し、爆発的に増加する「負のスパイラル」に陥りやすくなります。
以前は「ユリ科」として分類されていましたが、近年のDNA解析などによる研究の進展で、玉ねぎやネギの仲間は「ヒガンバナ科」に再分類されました。文献によっては旧分類のユリ科と記載されている場合もありますが、同じ仲間であることに変わりはありません。
共通する主要な病害虫とその被害
玉ねぎとネギ類の間で特に問題となる代表的な病害虫には、以下のようなものがあります。これらが一度圃場に蔓延すると、防除が非常に困難になるケースも少なくありません。
ネギアザミウマ
体長1〜2mmほどの非常に小さな害虫で、葉の汁を吸って食害します。被害を受けた部分は銀白色のかすり状になり、光合成能力が低下して生育不良を引き起こします。さらに、ウイルス病を媒介することもあり、二次的な被害も深刻です。
ネギハモグリバエ
幼虫が葉の内部に潜り込み、不規則な白い筋状の食害痕を残すため「エカキムシ」とも呼ばれます。被害が激しいと葉全体が白っぽくなり、光合成が阻害されて球の肥大に悪影響を及ぼし、品質を著しく低下させます。
萎縮病(ウイルス病)
アブラムシによって媒介されるウイルスが原因で発生します。感染すると葉が黄色く縮れて生育が極端に悪くなり、商品価値のある大きさまで育つことはほとんど期待できません。一度発病すると治療法がないため、原因となるウイルスの媒介者を圃場に入れない、増やさないといった予防が全てとなります。
黒腐菌核病(土壌病害)
土壌中に潜むカビ(糸状菌)が原因で、地際部から腐敗が始まり、やがて株全体が枯死します。病斑部には黒いゴマ粒のような菌核が多数形成され、これが土壌中で長期間生存するため、一度発生すると根絶が難しい厄介な病気です。
玉ねぎの収穫後、土壌中にはこれらの病害虫や病原菌が残存します。そこで翌年、同じ仲間である長ネギなどを栽培すると、待ち構えていた病害虫がすぐに活動を開始できる格好の環境を提供することになります。これにより、前年よりもさらに高い密度で病害虫が発生し、被害が甚大化します。そして、その圃場はさらに汚染が進むという、まさに「負のスパイラル」に陥ってしまうのです。
このような理由から、収量や品質の低下による直接的な経済的損失を防ぐためにも、玉ねぎと他のネギ類を同じ圃場で連続して栽培するローテーションは絶対に避けるべきです。輪作計画を立案する際には、必ず間にナス科やウリ科といった全く異なる科の作物を数年間挟むようにしてください。これは単なる栽培上の工夫ではなく、圃場の生産性を長期的に維持するための不可欠な投資と言えるでしょう。

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/
玉ねぎの連作障害を回避する後作計画
- 後作に植えて良い野菜の条件
- 土壌改善など具体的な連作対策
- 玉ねぎと特に相性の良い野菜
- 避けるべき後作に悪い野菜とは
後作に植えて良い野菜の条件


玉ねぎの後作を選ぶ際の最も重要な条件は、「科が異なる野菜」を選ぶことです。これは、連作障害の主要な原因である、特定の病害虫の増加や土壌養分の偏りをリセットするための、輪作における基本的な考え方です。
また、栽培時期も重要な選定基準となります。玉ねぎの収穫は、品種にもよりますが一般的に5月下旬から6月頃に行われます。このため、その後すぐに植え付けや種まきができ、夏から秋にかけて収穫期を迎える作物が、圃場を効率的に利用する上で最適です。
後作選びの2大条件
- 科が違うこと:ヒガンバナ科以外の作物を選ぶ。
- 栽培時期が合うこと:初夏に植え付けを開始できる作物を選ぶ。
土壌改善など具体的な連作対策


連作障害のリスクを低減し、持続的な土地利用を可能にするためには、積極的な土壌管理が不可欠です。後作の選定と合わせて、以下の対策を計画的に実施しましょう。
完熟堆肥の投入
土壌中の微生物の多様性を高めることが、特定の病原菌の増殖を抑制する上で非常に効果的です。牛ふんやバークなどの完熟した堆肥を十分に投入し、土壌の団粒構造を促進させましょう。これにより、通気性や排水性も改善されます。
太陽熱消毒
玉ねぎの収穫後、次の作付けまでの夏場の期間を利用した対策です。圃場に水をまいて十分に湿らせた後、透明なビニールマルチで覆います。梅雨明け後の強い日差しを利用して地温を60℃近くまで上昇させることで、土壌中の病原菌や害虫、雑草の種子を死滅させる効果が期待できます。
天地返し
作土層(通常15〜20cm)とその下にある下層土を物理的に入れ替える作業です。これにより、養分が枯渇した表層土を下に、まだ養分が残っている下層土を上に移動させ、土壌環境をリフレッシュさせることができます。
補足:緑肥の活用
後作までの期間に余裕がある場合は、ソルガムやエンバクといった緑肥作物を栽培するのも有効です。これらの作物を育てて収穫せずにそのまま土壌にすき込むことで、有機物が増え、土壌環境が改善されます。
玉ねぎと特に相性の良い野菜


玉ねぎの後作には、単に連作障害を避けるだけでなく、後作の生育を助けるといった付加価値が期待できる、相性の良い野菜が存在します。玉ねぎの根に共生する一部の細菌が、後作の土壌病原菌の密度を下げる効果を持つことや、玉ねぎが土壌の肥料分を適度に吸収してくれるため、後作の作物が「つるぼけ(茎葉ばかりが茂り、実がつかない状態)」しにくくなるメリットがあります。
| 野菜名 | 科 | 相性が良い理由 |
|---|---|---|
| サツマイモ | ヒルガオ科 | 連作に強く、肥料が少ない土壌を好む。栽培時期も最適。 |
| カボチャ | ウリ科 | つるぼけしにくく実付きが良くなる。立枯病が発生しにくくなる。 |
| ナス・ピーマン | ナス科 | 栽培期間が長く、夏から秋まで収穫を楽しめる。 |
| オクラ | アオイ科 | 栽培管理が比較的容易で、収穫期間も長い。 |
| ダイコン | アブラナ科 | 秋作のタイミングに合う。根が深く伸びるため土壌構造を改善する。 |
避けるべき後作に悪い野菜とは


一方で、玉ねぎの後作として栽培すると、双方の生育に悪影響を及ぼす可能性が高い野菜も存在します。これらを避けることは、輪作を成功させる上で非常に重要です。
ヒガンバナ科(ネギ類)
前述の通り、長ネギ、ニンニク、ニラ、ラッキョウなど、玉ねぎと同じ科の野菜は絶対に避けるべきです。共通の病害虫が圃場に蔓延し、壊滅的な被害につながるリスクが極めて高くなります。
マメ科
エダマメ、インゲンマメ、ソラマメ、エンドウなどのマメ科植物も、玉ねぎの後作には推奨されません。その理由は、マメ科植物の根に共生し、空気中の窒素を固定する働きを持つ「根粒菌」と、玉ねぎの根に共生する微生物との相性が悪いとされているためです。玉ねぎを栽培した後の土壌では、根粒菌の活動が阻害され、マメ科植物の生育が悪くなる可能性があります。
| 避けるべき野菜 | 科 | 避けるべき理由 |
|---|---|---|
| ネギ、ニンニク、ニラなど | ヒガンバナ科 | 共通の病害虫が蔓延し、連作障害のリスクが著しく高まる。 |
| エダマメ、ソラマメなど | マメ科 | 玉ねぎの後の土壌では、マメ科の生育に必要な根粒菌の働きが阻害される可能性がある。 |
【野菜別】玉ねぎの後作・連作の適性
- じゃがいもと玉ねぎの連作リスク
- 玉ねぎの後作にジャガイモは不向き
- さつまいもは連作障害がなく玉ねぎ後作に最適
- メリットが多い後作の大根栽培
- 育てやすい後作野菜ならオクラ
- 後作ではないが混植したい人参
- 正しい輪作で玉ねぎの連作障害を防ぐ
じゃがいもと玉ねぎの連作リスク


じゃがいも(ナス科)と玉ねぎ(ヒガンバナ科)は科が異なるため、両者を同じ圃場で栽培しても、直接的な連作障害のリスクは低いと言えます。共通する重大な病害虫も少ないため、輪作の組み合わせとしては問題ありません。
ただし、一点注意すべきなのが土壌酸度(pH)です。玉ねぎの生育に適した土壌pHが6.0〜6.5の中性付近であるのに対し、じゃがいもはそうか病の発生を抑えるために、pH5.0〜6.0のやや酸性寄りの土壌で栽培されるのが一般的です。
土壌pHの管理に注意
玉ねぎ栽培のために石灰を施してpHを調整した圃場で、そのままじゃがいもを栽培すると、そうか病のリスクが高まる可能性があります。逆に、じゃがいも栽培後の酸性土壌で玉ねぎを栽培すると、生育不良を起こすことがあります。両者を輪作体系に組み込む場合は、都度、適切なpH調整が必要になります。
玉ねぎの後作にジャガイモは不向き


前述の土壌pHの問題に加え、栽培時期の観点からも、玉ねぎの直後の後作としてジャガイモを栽培するのはあまり効率的ではありません。一般的な春ジャガイモの植え付け時期は2月〜3月であり、5月〜6月に収穫する玉ねぎの後作にはタイミングが合いません。
玉ねぎ収穫後に植え付けが可能なのは「秋ジャガイモ」になりますが、秋ジャガイモは栽培期間が短く、また高温期に植え付けを行うため、春ジャガイモに比べて収量が少なくなる傾向があります。圃場の利用効率や収益性を考慮すると、玉ねぎの後作としては、他の夏野菜を選択する方が合理的と言えるでしょう。
さつまいもは連作障害がなく玉ねぎ後作に最適


玉ねぎの後作として、最も推奨できる作物の一つがさつまいもです。さつまいもが後作に最適な理由は複数あります。
まず、さつまいも自身が非常に連作に強い作物(ヒルガオ科)である点です。さらに、肥料をあまり必要としないため、玉ねぎが土壌中の余分な肥料分を吸収してくれた後の「肥料切れ」に近い状態の圃場を好みます。肥料が多すぎると「つるぼけ」を起こしやすいさつまいもにとって、玉ねぎの跡地はまさに理想的な環境なのです。
栽培時期も5月〜6月に苗を植え付けるため、玉ねぎの収穫後、間を置かずに栽培を開始できます。これらの理由から、さつまいもは玉ねぎの後作として非常に相性が良いと言えます。
メリットが多い後作の大根栽培


大根(アブラナ科)も、玉ねぎの後作として優れた選択肢です。玉ねぎの収穫後に圃場を整備し、8月下旬から9月上旬に種をまく「秋大根」として栽培することで、スムーズな輪作が可能になります。
大根を後作にするメリットは、その深く伸びる根にあります。大根の直根が土中深くまで侵入することで、硬くなった土壌を物理的に耕し、通気性や排水性を改善する効果(生物的耕耘)が期待できます。また、玉ねぎが利用する表層の養分と、大根が利用する深層の養分が異なるため、土壌の養分バランスを整える上でも有効です。
玉ねぎの収穫から大根の種まきまで少し期間が空くので、その間に太陽熱消毒や堆肥の投入など、じっくり土づくりができるのも利点ですね。
育てやすい後作野菜ならオクラ


栽培管理の手間をあまりかけずに、安定した収穫を目指したい場合にはオクラ(アオイ科)がおすすめです。オクラは高温を好むため、玉ねぎ収穫後の初夏の気候は植え付けに最適です。
オクラの大きな魅力は、比較的病害虫の被害が少なく、栽培が容易である点です。また、一度収穫が始まると、霜が降りる10月頃まで次々と実をつけ続けるため、長期間にわたって収穫を楽しむことができます。圃場を長く有効活用できるという点で、経済的にも優れた作物です。
後作ではないが混植したい人参


人参(セリ科)は、玉ねぎの後作としてではなく、一緒に栽培する「コンパニオンプランツ」として非常に優れた相性を持ちます。
玉ねぎの持つ独特の香りは、人参に被害を及ぼす害虫(ネキリムシなど)を遠ざける効果があるとされています。一方で、人参の香りも玉ねぎの害虫であるタマネギバエを寄せ付けにくくする効果があると言われており、お互いの生育を助け合う共栄関係を築くことができます。玉ねぎの畝の間に人参を栽培する「混植」は、農薬の使用を減らす上でも有効な栽培技術です。
混植の注意点
混植を行う場合、玉ねぎを収穫する際に人参の根を傷つけないよう注意が必要です。また、お互いの株間を十分に確保し、風通しや日当たりが悪くならないように管理することが大切です。
正しい輪作で玉ねぎの連作障害を防ぐ


- 玉ねぎは連作に強いが3〜4年目から注意が必要
- 連作障害は土壌成分の偏りや特定の病原菌増加が原因
- 同じヒガンバナ科(ネギ類)の連作は絶対に避ける
- 後作の基本は科の異なる野菜を選ぶこと
- 玉ねぎの収穫時期(初夏)に植えられる作物が適している
- 土壌改良や太陽熱消毒などの対策も並行して行う
- 後作にはサツマイモ、カボチャ、ナス、オクラなどが最適
- サツマイモは肥料が少ない土壌を好み玉ねぎの後作に理想的
- 大根は土壌構造を改善する効果も期待できる
- 後作にマメ科の野菜は根粒菌との相性から推奨されない
- じゃがいもは土壌pHの好みが違うため管理に注意が必要
- 人参は後作ではなくコンパニオンプランツとして混植が有効
- 連作障害のリスクは圃場の状態によって変動する
- 前年の収量や品質をみて輪作を判断することが重要
- 計画的な輪作体系を組むことが持続的な農業経営の鍵となる

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/






