土壌改良や持続可能な農業に関心を持つ中で、「緑肥」という言葉を耳にする機会も増えたのではないでしょうか。緑肥は多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットや失敗につながる落とし穴も存在します。緑肥とは何か、そのメリットを理解しつつも、正しいやり方や自分の目的に合った種類の選び方を知らなければ、期待した効果が得られないかもしれません。特に、おすすめされるがままに導入して失敗したというケースも少なくありません。
そこでこの記事では、「緑肥 デメリット」というキーワードで検索されているあなたのために、緑肥の基本的な知識から、栽培で得られるメリット、そして特に注意すべきデメリットと失敗の原因まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの畑に最適な緑肥の種類を見つけ、デメリットを最小限に抑える正しいやり方を身につけることができるでしょう。
- 緑肥のメリットとデメリットの両側面
- 緑肥栽培で失敗する原因と対策
- 目的に合った緑肥の種類と選び方
- デメリットを最小限にするための正しいやり方
緑肥のデメリットを知り、失敗を防ぐ
- 【結論】知っておくべき緑肥の主なデメリット
- そもそも緑肥とは何か
- 緑肥栽培がもたらすメリット
- 緑肥作物の主な効果一覧
- 緑肥に使われる作物の種類
- 緑肥の失敗でよくある事例
- 緑肥作物の雑草化リスク
【結論】知っておくべき緑肥の主なデメリット

緑肥には多くのメリットがある一方、導入前に理解しておくべき主なデメリットが存在します。結論から言うと、デメリットは以下の4点に集約されます。
- 栽培の手間とコストがかかる:種子代や栽培・すき込みの労力が発生します。
- 後作物の生育を阻害するリスク:すき込み後の腐熟期間が不十分だと、作物の発芽や成長を妨げます。
- 意図しない雑草化の恐れ:繁殖力の強い種類は、管理を怠ると畑全体に広がり、除去が困難になります。
- 病害虫や相性の問題:後作物と共通の病害虫を増やしたり、他の植物の生育を抑制(アレロパシー効果)したりすることがあります。
ただし、これらのデメリットは、緑肥の特性を理解し、正しい種類選びとやり方を行うことで、その多くを回避・軽減することが可能です。以降の見出しで、これらのデメリットの詳細と具体的な対策について詳しく解説していきます。
そもそも緑肥とは何か

緑肥(りょくひ)とは、栽培した植物を収穫せず、生育途中の生の状態でそのまま土壌にすき込むことで、後から栽培する作物の肥料にしたり、土壌そのものを改良したりする方法のことです。化学肥料や堆肥とは異なり、植物そのものの力を利用して土づくりを行う、環境保全型の農法として古くから活用されてきました。
主な目的は、土壌に有機物を補給し、微生物の活動を活発にすることです。緑肥作物が土の中で分解される過程で、土がふかふかになる団粒構造が促進され、水はけや保水性の改善につながります。また、マメ科の緑肥のように、空気中の窒素を土壌に固定して肥料成分を供給するといった重要な役割も担っています。
堆肥との違い
堆肥は、刈り取った草や落ち葉、家畜ふんなどを一度堆積・発酵させてから畑に施用します。一方、緑肥は畑で育てた植物を直接すき込むため、堆肥を作る場所や手間が不要という利点があります。
このように、緑肥は土を育て、地力を維持・向上させるための有効な手段の一つとして、多くの農家に取り入れられています。
緑肥栽培がもたらすメリット

緑肥を栽培することには、単に肥料成分を補給するだけではない、多くのメリットが存在します。これらを理解することで、緑肥の価値をより深く知ることができるでしょう。
① 土壌の物理的改善
緑肥作物の根は、土壌を深く耕す役割を果たします。特にソルゴーのように深く根を張る作物は、トラクターでも届かない硬い土層(耕盤層)を破砕し、水や空気の通り道を確保します。また、すき込まれた有機物が分解されることで、土の粒子が集まってできる「団粒構造」が発達し、作物の根が伸びやすい、ふかふかで水はけ・保水性に優れた土壌へと変化していきます。
② 化学肥料の削減(減肥)
特にヘアリーベッチやクローバーなどのマメ科植物は、根に共生する根粒菌の働きによって、空気中の窒素を植物が利用できる形に変えて土壌に固定します。この窒素固定能力により、後作で必要となる窒素肥料の量を大幅に削減することが可能です。これはコスト削減だけでなく、環境負荷の低減にもつながる大きなメリットです。
③ 病害虫や雑草の抑制
一部の緑肥作物には、特定の病害虫の密度を減らす効果があります。例えば、エンバクはネグサレセンチュウ、マリーゴールドはネコブセンチュウの抑制効果が知られています。また、ヘアリーベッチなどが持つ「アレロパシー(他感作用)」という、他の植物の生育を抑制する化学物質を放出する能力は、雑草の発生を防ぐのに役立ちます。
緑肥が地面を覆う「リビングマルチ」としての効果も期待できます。これにより、雑草が光合成を行うのを物理的に防ぎ、除草の手間を省くことにも繋がりますよ。
緑肥作物の主な効果一覧

緑肥作物は種類によってそれぞれ異なる特性や効果を持っています。ここでは、代表的な緑肥作物とその効果を一覧でご紹介します。ご自身の畑の課題や目的に合わせて、最適な緑肥を選ぶ際の参考にしてください。
| 作物名 | 科 | 主な効果・特徴 |
|---|---|---|
| クロタラリア | マメ科 | 窒素固定、サツマイモネコブセンチュウ抑制 |
| ヘアリーベッチ | マメ科 | 窒素固定、アレロパシーによる雑草抑制、景観向上 |
| クリムゾンクローバー | マメ科 | ダイズシストセンチュウ抑制、景観向上、窒素固定 |
| ソルゴー(ソルガム) | イネ科 | 有機物量が豊富、深根による土壌物理性の改善、過剰肥料の吸収 |
| エンバク(燕麦) | イネ科 | キタネグサレセンチュウ抑制、分解が早い |
| ライムギ | イネ科 | 耐寒性が強い、キタネグサレセンチュウ抑制、リビングマルチ利用 |
| ヒマワリ | キク科 | リン酸吸収促進、深根による透水性改善、景観向上 |
| チャガラシ(カラシナ) | アブラナ科 | 土壌病害菌の抑制(土壌くん蒸効果) |
緑肥に使われる作物の種類

緑肥として利用される植物は、主に「イネ科」「マメ科」、そしてそれ以外の「キク科」や「アブラナ科」などに大別されます。それぞれの科に特有の性質があるため、特徴を理解しておきましょう。
イネ科
ソルゴー、エンバク、ライムギ、大麦などが代表的です。イネ科の作物は、多くの有機物を生産する能力に長けているのが特徴です。すき込むことで土壌の炭素源となり、微生物のエサを豊富に供給します。また、根が広く深く張るため、土壌の団粒化を促進し、物理性を改善する効果が高いです。特に土が硬い圃場や、有機物が不足している場合に適しています。
マメ科
ヘアリーベッチ、クローバー、レンゲ、クロタラリアなどが含まれます。マメ科の最大の特徴は、前述の通り根粒菌による窒素固定能力です。これにより、化学肥料に頼らずとも土壌の窒素分を増やすことができます。後作で窒素を多く必要とする葉物野菜などを栽培する前に導入すると、大きな減肥効果が期待できます。
その他(キク科、アブラナ科など)
ヒマワリやマリーゴールド(キク科)、チャガラシ(アブラナ科)なども緑肥として利用されます。これらの作物は、特定のセンチュウ抑制効果や、病原菌の密度を低下させる土壌くん蒸効果など、特有の機能を持つことが多いです。特定の土壌病害に悩んでいる場合に、対抗策として導入が検討されます。
緑肥の失敗でよくある事例

多くのメリットがある緑肥ですが、やり方を間違えると期待した効果が得られないばかりか、かえってマイナスの影響を及ぼすこともあります。ここでは、緑肥栽培でよくある失敗事例を見ていきましょう。
後作物の生育阻害
最も多い失敗が、すき込み後の腐熟期間が不十分なことです。緑肥をすき込むと、土壌中の微生物が分解を始めますが、この過程でガスが発生したり、一時的に土壌中の窒素が微生物に取り込まれたり(窒素飢餓)します。この状態で種をまいたり苗を植えたりすると、発芽不良や初期生育の遅れを引き起こします。特にイネ科のように炭素率の高い緑肥をすき込んだ際は注意が必要です。
収量減少の可能性
緑肥の選択を誤ることも失敗の原因です。例えば、後作の作物と共通の病害虫を増やす緑肥を選んでしまうと、病気の発生を助長しかねません。また、ヘアリーベッチのアレロパシー効果は強力な雑草抑制になりますが、レタスなどの発芽も阻害することがあります。緑肥と後作の相性を考えずに導入すると、収量減少に直結するリスクがあります。
コストと手間の増加
緑肥栽培には、当然ながら種子代や播種、管理、すき込みといった作業の手間とコストがかかります。特に草丈が高くなるソルゴーなどは、専用の裁断機(ハンマーナイフモアなど)がないと、すき込み作業が非常に困難になります。「とりあえずやってみよう」と始めると、想定外のコストや労力に直面する可能性があります。
緑肥作物の雑草化リスク

緑肥のデメリットとして特に注意したいのが、栽培した緑肥そのものが「雑草化」してしまうリスクです。緑肥作物は生育が旺盛で繁殖力が強いものが多いため、一度畑に導入すると、意図しない場所で増え続けてしまうことがあります。
特に問題となりやすいのが、ホワイトクローバーのような多年草です。ホワイトクローバーは、ほふく茎(ランナー)を伸ばして横に広がり、節々から根を出して定着します。そのため、一度畑に広がると完全に除去するのが非常に困難です。自分の区画だけでなく、隣の畑にまで侵食してしまうトラブルに発展するケースもあります。
貸し農園や、管理が難しい場所では、ホワイトクローバーのような多年草の緑肥は避けるのが賢明です。緑肥を選ぶ際は、クリムソンクローバーのような一年草を選ぶようにしましょう。一年草であれば、種がこぼれる前にすき込んでしまえば、翌年以降に意図せず繁殖するリスクを大幅に減らすことができます。
外来種の緑肥が周辺の生態系に影響を与える可能性も指摘されています。緑肥を導入する際は、その植物が持つ特性をよく理解し、適切に管理することが求められます。

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/
緑肥のデメリットを避ける具体的な方法
- 緑肥作物ソルゴーの特徴と注意点
- ヘアリーベッチの雑草抑制効果
- 緑肥用クローバーの選び方
- おすすめの緑肥作物の選定ポイント
- 緑肥のデメリットを減らすやり方
緑肥作物ソルゴーの特徴と注意点

ソルゴー(ソルガム)はイネ科の緑肥で、その圧倒的な有機物生産量が最大の特徴です。草丈は品種によっては3メートル以上にもなり、すき込むことで大量の有機物を土壌に供給できます。また、根が1メートル以上も深く伸びるため、硬盤層を破砕し、土壌の透水性を劇的に改善する効果が期待できます。
さらに、窒素やカリウムなどの肥料成分を強力に吸収する性質(吸肥力)があるため、前作で投入した肥料が過剰に残っている圃場の「クリーニングクロップ」としても非常に有効です。
ソルゴー利用時の注意点
多くのメリットがある一方、注意点も存在します。まず、草丈が高く茎も硬くなるため、すき込みには相応の装備が必要です。家庭用の耕運機では歯が立たないことも多く、フレールモアなどで細かく裁断してからすき込むのが一般的です。また、生育が進むと茎が硬くなり分解されにくくなるため、出穂が始まる前の柔らかい時期にすき込むのがポイントです。塩類濃度が極端に高い土壌にすき込むと、逆に塩類障害を助長する危険性も指摘されています。
ヘアリーベッチの雑草抑制効果

ヘアリーベッチはマメ科の緑肥で、非常に強力な雑草抑制効果を持つことで知られています。この効果の源は、植物が放出する化学物質で他の植物の生育を抑える「アレロパシー」という作用です。ヘアリーベッチは春になると地面を覆い尽くすように繁茂し、そのアレロパシー作用と被覆効果で、他の雑草の発生を物理的・化学的に防ぎます。
マメ科であるため窒素固定能力も高く、すき込むことで後作への肥料効果も期待できます。美しい紫色の花を咲かせるため、景観作物としての価値も高いです。
特に果樹園の下草として利用されることが多いですね。除草剤の使用を減らし、土壌を肥沃にする一石二鳥の効果が狙えます。
ただし、前述の通り、このアレロパシー効果は雑草だけでなく、ホウレンソウやレタスといった一部の作物の発芽も抑制してしまうことがあります。後作に種から育てる作物を予定している場合は、すき込みから作付けまでの期間を十分に空けるなどの注意が必要です。
緑肥用クローバーの選び方

クローバーは緑肥として非常にポピュラーですが、種類によって性質が大きく異なるため、選び方を間違えると「雑草化」という大きなデメリットに繋がります。選ぶ際の最も重要なポイントは、「一年草」か「多年草」かを必ず確認することです。
クリムソンクローバー(一年草)
深紅の美しい花を咲かせる一年草のクローバーです。ダイズシストセンチュウの抑制効果があることでも知られています。一年草なので、種がこぼれる前にすき込めば、翌年以降に勝手に繁殖する心配がほとんどありません。景観も良く、管理がしやすいため、特に家庭菜園や貸し農園でおすすめされることが多い種類です。
ホワイトクローバー(多年草)
シロツメクサとして知られる多年草のクローバーです。地面を這うように広がるため被覆力が高く、雑草抑制効果に優れています。しかし、その繁殖力の強さが仇となり、一度定着すると根絶が非常に困難で、管理を怠るとあっという間に畑全体に広がってしまいます。自分の土地で、永続的なグラウンドカバーを目的とする場合以外は、安易な導入は避けるべきでしょう。
結論として、一般的な畑の土壌改良や窒素補給を目的とする場合は、管理が容易で雑草化リスクの低い一年草のクリムソンクローバーを選ぶのが最も安全で確実です。
おすすめの緑肥作物の選定ポイント
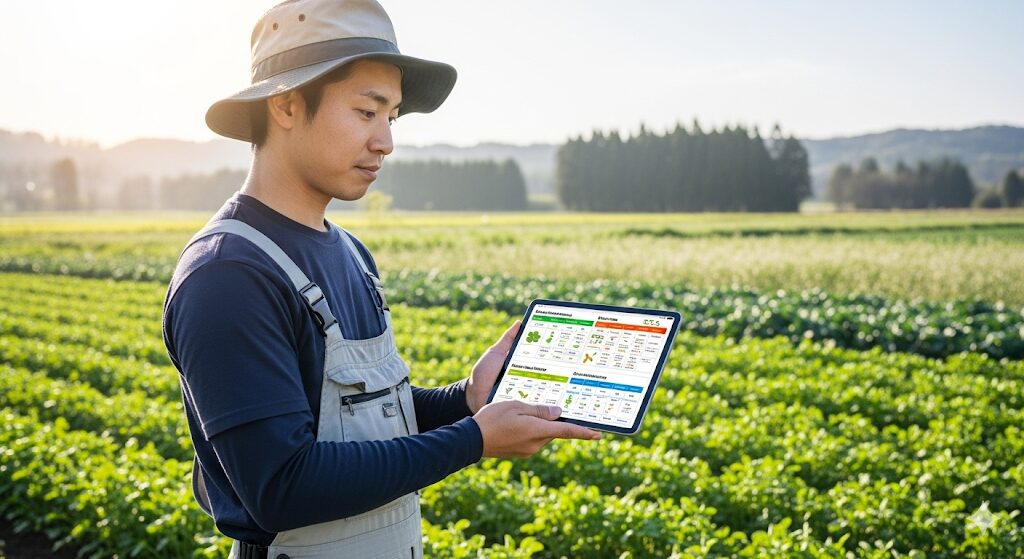
数ある緑肥の中から、自分の畑に最適なものを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。以下の3つのステップで考えてみましょう。
ステップ1:目的を明確にする
まず、なぜ緑肥を導入したいのか、その目的をはっきりさせることが最も重要です。
- 土をふかふかにしたい(物理性改善) → ソルゴー、エンバクなど
- 化学肥料を減らしたい(窒素補給) → ヘアリーベッチ、クローバーなど
- 特定のセンチュウを減らしたい → マリーゴールド、エンバクなど
- 雑草を抑制したい → ヘアリーベッチ、ライムギなど
ステップ2:栽培スケジュールを考える
緑肥を栽培するということは、その期間、主作物を栽培できないということです。主作物の作付け計画に合わせて、緑肥の播種時期とすき込み時期を決めましょう。「いつまでに、すき込みと腐熟を終わらせる必要があるか」から逆算して、その期間に栽培できる緑肥を選ぶ必要があります。
ステップ3:畑の環境を考慮する
自分の畑の土壌特性や環境も重要な選定基準です。例えば、排水性の悪い湿った畑では湿害に弱いヘアリーベッチは向きませんし、酸性土壌が強い場合は生育が悪くなる緑肥もあります。また、寒冷地か暖地かによっても、適した品種や播種時期は異なります。
初めてで何を選べば良いか分からない場合は、比較的育てやすく分解も早い「エンバク」や、窒素固定と雑草抑制の両方が期待できる「ヘアリーベッチ」あたりから試してみるのがおすすめです。
緑肥のデメリットを減らすやり方

- 緑肥は栽培植物を土にすき込み肥料や土壌改良に利用する方法
- メリットには土壌の物理性改善や化学肥料の削減がある
- 病害虫の抑制や雑草の繁茂を防ぐ効果も期待できる
- 主なデメリットは栽培の手間と種子代などのコストが発生すること
- すき込み時期を誤ると後作の生育を阻害するリスクがある
- 繁殖力の強い多年草は雑草化する可能性があるため注意が必要
- 緑肥の効果は土壌環境や地域の気候条件に左右される
- まず土壌改良や窒素補給など緑肥を導入する目的を明確にする
- 窒素固定が目的ならマメ科、有機物補給ならイネ科が基本の選び方
- センチュウ対策にはエンバクやマリーゴールドなどが有効とされる
- アレロパシー効果は雑草だけでなく後作物にも影響する場合がある
- すき込みはイネ科なら出穂前、マメ科なら開花前の柔らかい時期に行う
- ソルゴーなど草丈の高い緑肥は細かく裁断してからすき込むと分解が早い
- 自身の農地の課題と栽培スケジュールを把握し最適な緑肥を選ぶことが成功の鍵

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/






