大根の追肥時期について、具体的にいつ、どのように行えば良いかお悩みではありませんか。
家庭菜園や農業において、大根を大きく美味しく育てるためには、追肥のタイミングが非常に重要です。適切なやり方や回数を守らないと、肥料のやりすぎで根が割れたり、逆に大根の肥料不足のサインを見逃して生育が悪くなったりすることもあります。
また、大根の間引きと追肥は密接な関係にあり、種まき時期から収穫までの一連の流れを理解することが成功の鍵です。
この記事では、大根の肥料のやり方の基本から、鶏糞などの有機肥料の使い方、さらに追肥におすすめの肥料や、大根の肥料はいらないという説の真偽まで、プロの農家が実践する知識を基に詳しく解説します。
- 大根の生育段階に応じた追肥の最適なタイミング
- 追肥の具体的な方法と適切な施肥量
- 栽培状況に合わせたおすすめの肥料選び
- 肥料の過不足による失敗を防ぐための重要ポイント
収量を左右する大根の追肥時期の基本
- 栽培暦と最適な種まき時期
- 大根の間引きと追肥のタイミング
- 基本的な追肥のやり方と施肥量
- 適切な追肥の回数と土寄せ
- 元肥を含めた大根の肥料のやり方
栽培暦と最適な種まき時期
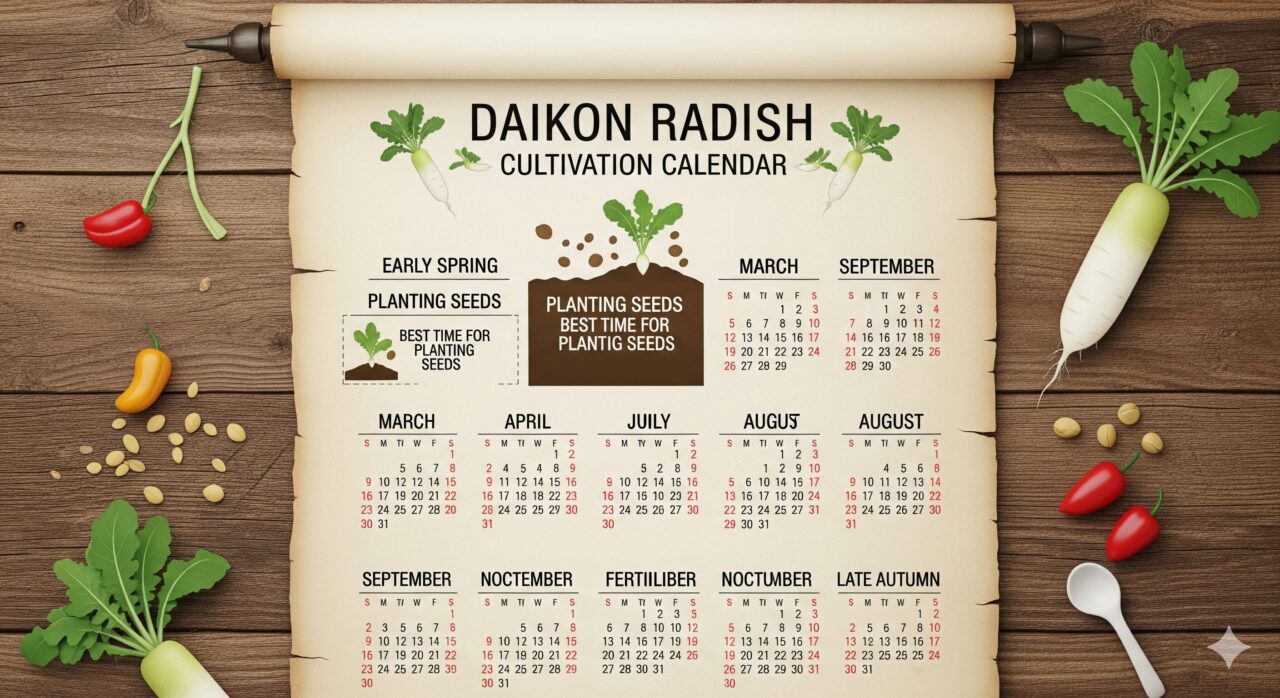
大根栽培を成功させるための第一歩は、適切な時期に種をまくことです。大根は本来、冷涼な気候を好む野菜であり、栽培に最適な気温は15~20℃とされています。このため、多くの品種にとって最も栽培しやすいのは秋まきです。
関東地方のような平地では、9月の上旬から中旬が秋まきの最適期となります。この時期に種をまくと、発芽後の生育初期に厳しい残暑を避けられ、気温が下がるにつれて根がじっくりと肥大するための理想的な環境が整います。
もちろん、品種を選べば春まきや夏どりも可能ですが、春まきは低温による「トウ立ち(花芽ができてしまうこと)」のリスクがあり、夏どりは高温や病害虫の対策がより重要になります。特に農業として安定した収量と品質を目指すのであれば、主力品種は秋まきで計画するのが基本です。
播種から収穫までの期間は品種によって異なりますが、一般的にはおよそ60日から100日程度が目安です。この栽培スケジュールを念頭に置き、追肥や間引きなどの管理計画を立てることが重要になります。
大根の間引きと追肥のタイミング

大根栽培において、間引きと追肥は一連の作業として捉えることが非常に重要です。間引きで株の生育環境を整えた直後に追肥を行うことで、残した株の成長を力強く後押しできます。
間引きは、密植状態を解消し、健全な株に栄養を集中させるために行います。一般的に2〜3回に分けて実施します。
- 1回目の間引き:本葉が2~3枚の頃。生育の良い株を3本残します。
- 2回目の間引き:本葉が6~7枚の頃。さらに1本を間引き、最も生育が良く、まっすぐ伸びている株を1本だけ残します。(これを「一本立ち」と呼びます)
そして、追肥を行う最適なタイミングは、この間引きの直後です。特に2回目の間引きを終え、一本立ちにした後は、根が本格的に肥大を始める重要な時期にあたります。このタイミングで追肥をすることで、肥料成分が無駄なく吸収され、根の成長を効果的に促進させることができるのです。
土寄せも忘れずに
間引きと追肥を行った後は、株元に土を寄せる「土寄せ」も必ず行いましょう。これにより、株のぐらつきを防ぎ、根がまっすぐに伸びるのを助ける効果があります。
基本的な追肥のやり方と施肥量

追肥のやり方は、栽培方法によって少し異なりますが、基本は「根に直接肥料が触れないように施す」ことです。根に肥料が直接当たると「肥料やけ」を起こし、生育を阻害する原因となるため注意が必要です。
マルチ(畑の表面を覆うビニールシート)を使用している場合は、畝と畝の間、またはマルチの縁に沿って肥料をまきます。これを「条間施肥」と呼びます。施肥量は、1平方メートルあたり化成肥料(N-P-K=8-8-8など)を約50gが目安です。
肥料をまいた後は、土の表面を軽く耕す「中耕」を行うと、肥料が土と混ざりやすくなるだけでなく、土中に酸素が供給されて根の呼吸を助ける効果も期待できます。
追肥の際は、肥料が株の葉や茎にかからないように気をつけましょう。もし葉の上に乗ってしまった場合は、手で優しく払いのけてあげてくださいね。
施肥量はあくまで目安であり、土壌の状態や大根の生育状況を見ながら調整することが大切です。葉の色が薄いなど、肥料不足のサインが見られる場合は、少し量を増やすなどの対応が必要になります。
適切な追肥の回数と土寄せ

大根栽培における追肥の回数は、基本的に2回行うのが一般的です。多すぎても少なすぎても生育に影響が出るため、適切なタイミングで必要な回数を実施することが収量アップにつながります。
追肥のタイミングと作業内容を以下の表にまとめました。
| 追肥の回数 | タイミングの目安 | 主な作業内容 |
|---|---|---|
| 1回目 | 2回目の間引き後(本葉5~6枚) | 化成肥料を条間に施し、中耕と土寄せを行う。 |
| 2回目 | 1回目の追肥から約2~3週間後(本葉10~15枚) | 同様に化成肥料を施し、土寄せを行う。この時期の土寄せは、根の肩部分が地上に露出し、緑色になる「青首」を防ぐ効果もある。 |
ただし、これは一般的な早生種や中生種の場合です。収穫までの期間が長い中〜晩生種を栽培する場合は、生育期間が長いため3回、場合によっては4回の追肥が必要になることもあります。栽培する品種の特性をよく理解し、生育状況を観察しながら追肥計画を調整することが求められます。
前述の通り、追肥と土寄せはセットで行うのが基本です。土寄せを丁寧に行うことで、大根が倒れるのを防ぎ、まっすぐで形の良い大根に育てることができます。
元肥を含めた大根の肥料のやり方

追肥の効果を最大限に引き出すためには、その土台となる元肥(もとごえ)が非常に重要です。元肥とは、種まきや植え付けの前にあらかじめ畑に施しておく肥料のことで、生育初期の成長を支える役割を担います。
大根の土づくりと元肥の施し方は、以下の手順で行うのが理想的です。
- 土壌改良(種まきの2週間〜1ヶ月前): 1平方メートルあたり、完熟堆肥を約2kg、苦土石灰を100〜150g(2〜3握り)を畑全体に散布し、深さ30cmほどまでよく耕します。
- 元肥の投入(種まきの1週間前): 1平方メートルあたり、化成肥料(N-P-K=8-8-8など)を約150g(3握り)を施し、再び深く耕して土と肥料をしっかり混ぜ合わせます。
未熟な堆肥は避けること
土づくりに使用する堆肥は、必ず十分に発酵・分解が進んだ「完熟堆肥」を使用してください。未熟な堆肥を施すと、土の中で分解される過程でガスが発生し、若い根を傷つけて生育不良や「岐根(またわれ)」の原因になります。
大根栽培で目指すべきは、窒素・リン酸・カリウムがバランスよく含まれた土壌環境です。特に窒素成分が多すぎると、葉ばかりが茂ってしまい、肝心の根が太りにくくなる「葉ボケ」という状態になりやすいので注意しましょう。

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/
高品質な大根を目指す追肥時期と肥料
- 見逃せない大根の肥料不足のサイン
- 根割れの原因となる肥料のやりすぎ
- 追肥はいらないという説は本当か
- 有機肥料として鶏糞を使う注意点
- 農家が使う大根肥料のおすすめ
- 即効性が重要となる追肥 おすすめ肥料
見逃せない大根の肥料不足のサイン

大根の生育状況を注意深く観察することで、肥料が不足しているサインを読み取ることができます。追肥のタイミングを計る上で重要な指標となるため、日々の見回りで確認する習慣をつけましょう。
最も分かりやすいサインは、葉の状態です。健全な大根の葉は、地面に対して約45度の角度を保ち、生き生きと立ち上がっています。もし葉が力なく垂れ下がったり、全体的に色が薄く黄色っぽくなったりしている場合は、肥料、特に窒素成分が不足している可能性があります。
また、生育全般の遅れもサインの一つです。同じ時期に種をまいた周りの株と比べて、明らかに葉の枚数が少なかったり、大きさが小さかったりする場合は、肥料不足が考えられます。このようなサインを見つけたら、通常よりも少し早めに追肥を行うなどの対策を検討する必要があります。
根割れの原因となる肥料のやりすぎ

「たくさん肥料を与えれば、それだけ大きな大根が採れる」と考えるのは間違いです。むしろ、大根は肥料のやりすぎによって様々な生育障害を引き起こしやすい野菜です。
肥料過多による主な生育障害
- 根の割れ(裂根): 肥料が効きすぎると根の肥大スピードが急激になり、表面の成長が追いつかずに亀裂が入ってしまいます。特に収穫間近の追肥や、降雨後の多湿状態での追肥は根割れのリスクを高めます。
- 地上部の過繁茂(葉ボケ): 窒素肥料が多すぎると、栄養が葉にばかり集中してしまい、肝心の根が十分に太りません。
- 岐根(股根): 元肥や追肥で施した肥料が土の中で塊になっていると、伸びてきた根がそれを障害物と認識し、避けるようにして伸びるため、根が二股や三股に分かれてしまいます。
- 食味の悪化: 肥料過多で育った大根は、繊維質が硬くなったり、苦味やえぐみが強くなったりする傾向があります。
これらの失敗を防ぐためにも、施肥量をきちんと守り、肥料が偏らないように均一に施すことが非常に重要です。特に、生育後半の追肥は慎重に行う必要があります。
追肥はいらないという説は本当か

「大根は肥料を与えすぎない方が良い」という話から派生して、「追肥はいらない」という説を聞いたことがあるかもしれません。この説には、一部真実も含まれています。
大根は野菜の中でも比較的、自ら土中の栄養分を吸収する力(吸肥力)が強い作物です。このため、前作の肥料が十分に土に残っている肥沃な畑であれば、元肥だけでもそこそこの大きさの大根を収穫することは可能です。
しかし、これはあくまで「土壌の条件が良い場合に限る」話です。毎年安定して、商品価値の高い、大きく形の良い大根を計画的に生産するためには、適切な追肥が不可欠です。
特に、生育のステージごとに必要な栄養素は変化します。生育後半、根がぐんぐん肥大する時期には多くの栄養を必要とするため、このタイミングで追肥を行わないと、肥大が途中で止まってしまい、小ぶりな大根しか収穫できない可能性が高くなります。無肥料・無追肥での栽培は、土壌の地力に大きく左右されるため、プロの農家が行う計画的な栽培には不向きと言えるでしょう。
有機肥料として鶏糞を使う注意点

有機栽培を目指す方にとって、鶏糞は安価で栄養価の高い魅力的な肥料です。結論から言うと、大根の肥料として鶏糞は「使えますが、使い方には十分な注意が必要」です。
鶏糞は窒素やリン酸、カリウムをバランス良く含み、さらに石灰(カルシウム)分も豊富です。しかし、その肥料成分の濃度が高いため、使い方を誤ると以下のようなデメリットが生じます。
- 肥料やけ: 分解が急激に進むため、根に直接触れると生育障害を起こしやすい。
- 岐根の原因: 未熟な鶏糞は土の中で塊になりやすく、岐根を誘発する。
- 土壌のアルカリ化: 石灰分が多いため、継続して使用すると土壌がアルカリ性に傾きやすい。(大根は弱酸性を好みます)
鶏糞を安全に使うためのポイント
鶏糞を大根栽培で用いる場合は、必ず以下のポイントを守ってください。
- 必ず「完熟発酵済み」のものを選ぶ。
- 追肥ではなく「元肥」として、種まきの1ヶ月以上前に施す。
- 畑全体に均一にまき、土としっかり混ぜ込む。
追肥として使用すると、ガス発生のリスクや肥料成分が急激に効きすぎるリスクがあるため、基本的には元肥として土づくりに活用するのが安全な使い方です。
農家が使う大根肥料のおすすめ

プロの農家が安定した品質の大根を栽培するために基本としているのは、特定の成分に偏らないバランスの取れた肥料です。家庭菜園でもこの考え方は同様に重要です。
基本はバランス型の化成肥料
最も一般的で使いやすいのが、窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)の成分比が「8-8-8」や「10-10-10」のように同率で配合された化成肥料です。これは元肥としても追肥としても使用でき、非常に汎用性が高いです。迷ったら、まずはこのタイプの肥料を選ぶと良いでしょう。
ホウ素欠乏に注意
大根はアブラナ科の野菜であり、生育過程で「ホウ素」という微量要素を必要とします。ホウ素が欠乏すると、根の表面に亀裂が入ったり、内部が褐色に変色して空洞ができる「褐色芯腐れ症」や「ス入り」の原因になります。
これを防ぐため、ホウ素をはじめとする微量要素が含まれた総合肥料を使用するのもおすすめです。毎年同じ畑で栽培している場合は、土壌診断を行い、ホウ素が不足しているようであれば、ホウ素単体の肥料を規定量施用することも有効な対策となります。
即効性が重要となる追肥 おすすめ肥料

元肥はじっくりと長期間効果が続く緩効性のものが理想ですが、追肥には施してから素早く効果が現れる「速効性」が求められます。
追肥におすすめなのは、やはり粒状の化成肥料です。水に溶けやすく、施肥後すぐに根から吸収され始めるため、生育が旺盛になるタイミングでタイムリーに栄養を供給することができます。
また、より速効性を求める場面では液体肥料(液肥)も有効です。水で希釈して株元に与えるため、吸収が非常に速いのが特徴です。ただし、効果の持続期間は短く、コストも割高になる傾向があるため、葉の色が悪いなど、緊急で栄養補給が必要な場合に補助的に使用するのが一般的です。
追肥専用の肥料も
市場には、生育後半に必要な窒素(N)とカリウム(K)を中心に配合した「NK化成」のような追肥専用の肥料も販売されています。これらは、根の肥大を特に促進させたい時期に効果的です。栽培規模や目指す品質に応じて、こうした専用肥料を使い分けるのも一つの方法です。
適切な大根の追肥時期で品質向上へ
この記事で解説した、大根の追肥に関する重要なポイントを以下にまとめます。
- 大根栽培の最適期は冷涼な気候を好むため秋まきが基本
- 種まきは関東平野部では9月上旬から中旬が目安
- 追肥のタイミングは間引きの直後が最も効果的
- 間引きは本葉2〜3枚と6〜7枚の計2回が基本
- 追肥の回数は生育期間中に2回行うのが一般的
- 1回目の追肥は2回目の間引き後(本葉5〜6枚)
- 2回目の追肥は1回目から約2〜3週間後が目安
- 追肥のやり方は根に直接触れないよう畝の間に施す
- 追肥と土寄せはセットで行い株の安定と根の伸長を助ける
- 肥料のやりすぎは根割れや岐根、食味悪化の原因となる
- 葉の色が薄くなったり垂れ下がったりするのは肥料不足のサイン
- 高品質な大根のためには元肥と追肥の両方が不可欠
- 鶏糞は完熟発酵済みのものを元肥として使用するのが安全
- おすすめの肥料はN-P-Kのバランスが取れた化成肥料
- 追肥には速効性のある粒状の化成肥料や液体肥料が適している

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/









