畑や家庭菜園で、てんとう虫に似た虫を見つけて
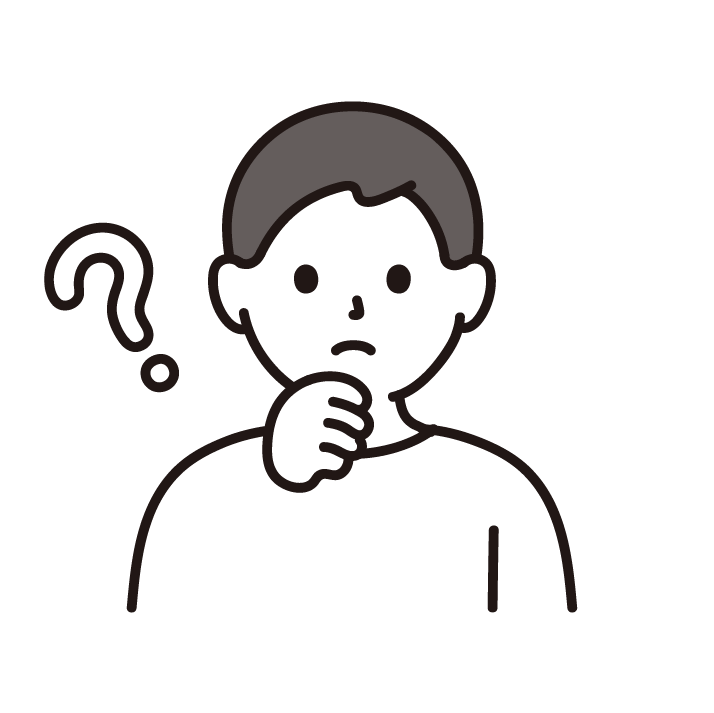
これって益虫?それとも害虫?
と悩んだ経験はありませんか?
益虫であれば大切にしたい一方、もし害虫であれば迅速な対策が必要です。
この記事では、農家や家庭菜園を営む方々に向けて、てんとう虫に似た害虫の正しい見分け方から、テントウムシダマシ駆除の具体的な方法までを詳しく解説します。
中にはカメムシの仲間や、人体への影響が気になる毒の有無、効果的な殺虫剤の選び方など、多くの方が抱く疑問にもお答えしていきます。
- てんとう虫に似た害虫と益虫の具体的な違い
- テントウムシダマシをはじめとする主要な害虫の特徴
- 農薬を使わない自然な駆除方法と予防策
- 効果的な殺虫剤の種類と比較
てんとう虫に似た害虫の種類と見分け方
- 益虫かどうかの簡単な見分け方
- 危険!オレンジ色のテントウムシダマシ
- てんとう虫に似たカメムシの存在
- 茶色や黒いてんとう虫みたいな虫
益虫かどうかの簡単な見分け方


てんとう虫には、アブラムシを食べてくれる益虫と、作物の葉を食い荒らす害虫が存在します。見分けるための最も重要なポイントは、体の「光沢」です。


アブラムシを捕食するナナホシテントウやナミテントウといった益虫の成虫は、体の表面がツヤツヤと輝いており、光沢があります。


一方で、ナスやジャガイモの葉を食べるニジュウヤホシテントウ(テントウムシダマシ)などの害虫は、体全体が細かい毛で覆われていて、光沢がなくマットな質感をしています。
この光沢の有無は、成虫を見分ける上で非常に分かりやすい指標となります。畑で見かけた際は、まず体のツヤをチェックしてみてください。
見分け方のポイント
- 益虫(肉食・菌食):体に光沢があり、ツヤツヤしている。
- 害虫(草食):体に光沢がなく、短い毛で覆われマットな質感。




また、幼虫の姿も大きく異なります。益虫であるナナホシテントウの幼虫は黒っぽくゴツゴツした見た目ですが、害虫のテントウムシダマシの幼虫は黄色っぽく、背中にトゲのような突起がたくさん生えているのが特徴です。この姿を見かけたら、成虫になる前に駆除することをおすすめします。
危険!オレンジ色のテントウムシダマシ


家庭菜園や農地で特に注意が必要なのが、オレンジ色の体を持つ「テントウムシダマシ」です。これは主にニジュウヤホシテントウやオオニジュウヤホシテントウを指す通称で、草食性の代表的な害虫として知られています。
これらのてんとう虫は、その名の通り28個の黒い斑点を持つことが特徴ですが、数えにくいことも多いです。そのため、「光沢のないオレンジ色のてんとう虫は害虫の可能性が高い」と覚えておくと良いでしょう。
彼らは特にナス科の作物を好み、被害に遭いやすい野菜は以下の通りです。
- ナス
- ジャガイモ
- トマト、ミニトマト
- ピーマン
テントウムシダマシの食害の特徴


テントウムシダマシの成虫と幼虫は、葉の裏側から表面の薄皮を残すように削り取って食べます。被害を受けた葉は、半透明の細かいスジが無数に入ったようになり、最終的には網目状になって枯れてしまうこともあります。生育初期に大きな被害を受けると、収穫量に深刻な影響が出るため、早期発見・早期駆除が不可欠です。
ニジュウヤホシテントウは比較的暖かい地域に、オオニジュウヤホシテントウは寒冷地に見られますが、どちらも農作物にとっては重大な脅威となります。
てんとう虫に似たカメムシの存在


てんとう虫と見間違えやすい虫の中には、カメムシの仲間も存在します。特にアブラナ科の野菜(コマツナ、ハクサイ、ダイコンなど)でよく見られるのが「ナガメ」や「ヒメナガメ」です。
これらのカメムシは、オレンジ色(または赤色)と黒の鮮やかな模様を持ち、一見するとてんとう虫のように見えます。しかし、形をよく見ると、てんとう虫の丸みを帯びた半球状の体つきとは異なり、やや角ばった五角形に近い形をしています。
ナガメは「菜の花につくカメムシ」が名前の由来とも言われています。見た目は綺麗ですが、作物の汁を吸う立派な害虫なので注意が必要ですね。


ナガメは作物の茎や葉に口吻(こうふん)と呼ばれる針のような口を刺して汁を吸います。被害を受けた部分は白い斑点となり、数が多いと作物がしおれてしまう原因にもなります。てんとう虫だと思って放置せず、形や模様をよく観察して正しく判断することが大切です。
もし見つけた数が少なければ、刺激して臭いを出す前にガムテープなどに貼り付けて捕獲するのが手軽で効果的です。
小さくて丸っこい「マルカメムシ」


また、大きささ丸っこい形がテントウムシに非常によく似ているのが、強い臭いを放つ「マルカメムシ」です。こげ茶色から黒色で、体は丸みを帯びていますが、よく見るとやや角ばっています。秋になると越冬のために暖かい場所を求めて家屋に集まり、洗濯物などに付着することが多い不快害虫です。
茶色や黒いてんとう虫みたいな虫
畑だけでなく、家の中やその周辺で、てんとう虫に似た茶色や黒い小さな虫を見かけることがあります。これらは、これまで紹介した害虫とはまた別の種類の可能性があります。
茶色いてんとう虫に似た虫:「ヒメマルカツオブシムシ」


白と茶色のまだら模様で、丸くて小さなこの虫は「ヒメマルカツオブシムシ」の成虫である可能性が高いです。成虫は花の蜜や花粉を食べるため、特にマーガレットやデージーといった白い花に集まる習性があります。


成虫自体に直接的な害はありませんが、問題となるのはその幼虫です。幼虫は羊毛や絹製品、毛皮といった衣類や、鰹節などの乾燥動物性食品を食べてしまいます。白い洗濯物などに付着して家の中に侵入し、クローゼットの中で繁殖することがあるため、注意が必要です。
黒いてんとう虫の正体は?益虫「ナミテントウ」と害虫の見分け方
黒くて丸い虫を見かけた場合、アブラムシなどを食べてくれる益虫の「テントウムシ」の仲間か、植物や衣類に害を及ぼす「てんとう虫に似た害虫」の、2つの可能性が考えられます。


一つは、益虫である「ナミテントウ」の黒色型です。ナミテントウは模様のバリエーションが非常に多く、黒い体に赤い点が2つや4つあるタイプなどが存在します。これらはアブラムシを食べてくれる益虫なので、駆除する必要はありません。見分けるための最も重要なポイントは体の光沢**です。表面がツヤツヤしていれば、ナミテントウの可能性が高いでしょう。
もう一つは、てんとう虫によく似た害虫の可能性です。代表的なものに以下の虫がいます。


- ヘリグロテントウノミハムシ 植物の葉を食べる害虫です。ナミテントウ(大きさ4~8mm)より一回り小さい3.5mm程度の大きさで、体の幅ほど長い触角を持ちます。刺激を与えると、てんとう虫が死んだふりをするのに対し、この虫はノミのように跳ねて逃げるのが大きな特徴です。
- カツオブシムシの仲間 家の中で見かけることが多い害虫です。特に「ヒメカツオブシムシ」は黒一色でてんとう虫に似ていますが、体がやや長く、光沢がありません。成虫に直接的な害は少ないですが、その幼虫が羊毛や絹製品といった衣類や乾燥食品を食害するため、注意が必要です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/
害虫の生態と家庭でできる予防策
- テントウムシダマシに毒はあるのか
- 家の中に発生する原因と対策
テントウムシダマシに毒はあるのか


畑で害虫であるテントウムシダマシを見つけた際、「刺されたりしないか」「毒はあるのか」と心配になる方もいるかもしれません。
結論から言うと、テントウムシダマシに人体へ影響を及ぼすような毒はありません。手で触れても刺されたり、毒でかぶれたりすることはないので、その点は安心してください。幼虫の見た目はトゲトゲしていますが、このトゲも柔らかく、皮膚に刺さることはありません。
しかし、危険を感じると脚の関節から黄色い液体を出すことがあります。これは独特の臭いを持つ忌避物質で、有害ではありませんが、手につくと臭いが取れにくい場合があります。駆除する際は、直接手で触れずに割り箸や手袋を使うと良いでしょう。
テントウムシダマシの「毒」は、あくまで農作物に対する「食害」という形で現れます。人間への直接的な危険性はありませんが、作物を守るためには迅速な駆除が必要不可欠です。
このように、テントウムシダマシは人間にとっての直接的な脅威ではありませんが、農業生産においては紛れもない害虫です。見つけ次第、放置することなく対処することが重要になります。
家の中に発生する原因と対策


「畑ではなく、家の中でてんとう虫に似た虫を見かける」という場合、その正体は前述の「ヒメマルカツオブシムシ」や「マルカメムシ」であることが多いです。
主な侵入経路
これらの虫が家の中に侵入する最も一般的な経路は、屋外に干している洗濯物への付着です。
- ヒメマルカツオブシムシの成虫:白い色を好む性質があるため、特にシーツやワイシャツ、タオルなど、白っぽい洗濯物に引き寄せられやすいです。
- マルカメムシ:秋に越冬場所を探して暖かい場所に集まる習性があり、日当たりの良い場所に干された洗濯物は格好の隠れ場所になります。
洗濯物を取り込む際に虫が付着していることに気づかず、そのまま室内に持ち込んでしまうことで発生につながります。
家庭でできる予防と対策
家の中での発生を防ぐためには、侵入させないことが第一です。
侵入防止策
- 洗濯物を取り込む前によくはたく:特に白い衣類や、虫が発生しやすい時期(ヒメマルカツオブシムシは春、マルカメムシは秋)には、家に入れる前に衣類を一枚ずつ軽く振ったり、表面をはらったりする習慣をつけましょう。
- 防虫ネットの活用:窓や換気口に目の細かい網戸や防虫ネットを設置し、物理的に侵入を防ぎます。
- 忌避剤の使用:洗濯物を干す場所に、カメムシなどが嫌うハーブ系の香りのする忌避剤を吊るしておくのも一つの方法です。
もし家の中でヒメマルカツオブシムシの幼虫(衣類を食べる害虫)を見つけた場合は、衣替えの際にクローゼットやタンスの衣類をすべて出して確認し、防虫剤を設置することが重要です。
てんとう虫に似た害虫への具体的な駆除方法
- テントウムシダマシ駆除の基本
- お酢を使ったスプレーでの予防
- 殺虫剤スミチオンとマラソンの比較
- まとめ:てんとう虫に似た害虫の早期対策
テントウムシダマシ駆除の基本


テントウムシダマシの被害を最小限に抑えるためには、「早期発見・早期駆除」が鉄則です。繁殖力が強く、放置するとあっという間に数が増えてしまいます。
駆除の基本は、成虫や幼虫、そして卵を見つけ次第、物理的に取り除くことです。
物理的駆除の方法
- 捕殺:数が少ないうちは、割り箸でつまんだり、ガムテープに貼り付けたりして捕獲するのが最も確実です。益虫を誤って駆除してしまうリスクもありません。
- 葉ごと除去:葉の裏に産み付けられた黄色い卵塊(20~30個の集まり)や、孵化したばかりで集まっている幼虫は、葉ごと切り取って処分するのが効率的です。
- 揺すり落とす:テントウムシダマシは、危険を感じると死んだふりをして地面に落ちる「擬死」という習性があります。株の下に袋や容器を広げておき、株を軽く揺すって虫を振り落として捕獲する方法も有効です。
特に春先、ジャガイモの芽が出始める頃から葉の裏をこまめにチェックする習慣をつけると、卵の段階で対処しやすくなりますよ。
耕種的防除
薬剤に頼る前に、栽培環境を整えることも重要です。
- 防虫ネットの利用:植え付け直後から収穫期まで、目の細かい(1mm以下が理想)防虫ネットでトンネル栽培をすることで、成虫の飛来と産卵を防ぎます。
- 風通しを良くする:株間を適切にとり、適宜整枝や葉かきを行うことで、風通しと日当たりを改善します。これにより害虫が隠れにくくなり、天敵(クモなど)に見つかりやすくなります。
- コンパニオンプランツ:近くにアブラナ科の野菜(キャベツやダイコン)を植えると、被害の拡大を抑えられる可能性があるという情報もあります。
お酢を使ったスプレーでの予防


「できるだけ化学農薬は使いたくない」と考える方には、身近な材料で作れる自然由来のスプレーがおすすめです。その代表格が、食用の「お酢(穀物酢)」を使ったスプレーです。
お酢に含まれる酢酸には、虫が嫌がる効果や、病原菌の繁殖を抑える静菌効果が期待できます。テントウムシダマシのような害虫に対する強い殺虫効果はありませんが、作物に寄り付きにくくする忌避剤として有効です。
お酢スプレーの作り方と使い方
【材料】
- 食用のお酢(穀物酢や米酢など、醸造酢を使用)
- 水
- スプレーボトル
【作り方】
水でお酢を25倍~50倍程度に薄めて、よく混ぜ合わせるだけです。例えば、500mlのスプレーボトルなら、お酢10ml~20mlに対して残りを水で満たします。
【使い方】
害虫の発生前や発生初期に、週に1~2回程度、葉の表裏にまんべんなく散布します。特に害虫が隠れやすい葉の裏側には念入りにスプレーしましょう。
使用上の注意点
- 濃度に注意:濃度が濃すぎると、作物の葉が傷んだり生育に影響が出たりする「薬害」の原因になります。必ず薄めて使用してください。
- 散布時間に注意:日中の暑い時間帯に散布すると、水分がレンズの役割をして葉が焼けてしまうことがあります。朝方や夕方の涼しい時間帯に散布するのがおすすめです。
- 効果の持続性:雨が降ると効果が流れてしまうため、天候を見ながらこまめに散布する必要があります。
トウガラシやニンニクを一緒に漬け込むと、さらに忌避効果が高まるとも言われています。化学農薬と比べて効果は穏やかですが、環境への負荷が少なく、安心して使える点が最大のメリットです。
殺虫剤スミチオンとマラソンの比較




害虫が大量に発生してしまい、物理的駆除や自然農薬だけでは対応が難しい場合には、化学農薬の使用も有効な選択肢となります。中でも「スミチオン」と「マラソン」は、家庭園芸からプロの農業現場まで広く使われている代表的な有機リン系殺虫剤です。
どちらも幅広い害虫に効果がありますが、それぞれに特徴があるため、状況に応じて使い分けることが重要です。
| 項目 | スミチオン乳剤 | マラソン乳剤 |
|---|---|---|
| 有効成分 | MEP(フェニトロチオン) | マラソン(マラチオン) |
| 特徴 | 効果の持続性が比較的長い。 浸透性があり、葉の中に潜んだ害虫にも効果が期待できる。 | 効果が現れるのが速い(速効性)。 残効性が比較的短く、分解が速い。 |
| 主な対象害虫 | アブラムシ類、テントウムシダマシ類、ヨトウムシ、アオムシなど広範囲。 | アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類など広範囲。 |
| 使用のポイント | 予防的な散布や、害虫の発生が長期間にわたる場合に向いています。 | 害虫を今すぐ駆除したい場合や、収穫までの期間が短い作物に向いています。 |
農薬使用時の最重要注意点
化学農薬を使用する際は、必ず製品ラベルを熟読し、記載されている内容を厳守してください。
- 対象作物と対象害虫:使用したい作物と、駆除したい害虫に農薬が登録されているか必ず確認します。
- 希釈倍数:定められた倍率より濃くしても効果は上がらず、薬害のリスクが高まるだけです。
- 使用時期と使用回数:収穫何日前まで使えるか、その作物に対して何回まで使えるかという制限を守ります。
- 安全装備:散布時はマスク、ゴーグル、手袋、長袖長ズボンを着用し、薬剤を吸い込んだり皮膚に付着したりしないよう注意してください。
農薬に関する最新の登録情報は、農薬登録情報提供システムなどで確認することをおすすめします。
どちらの薬剤もテントウムシダマシ類に登録があり有効ですが、同じ系統の薬剤を連続して使用すると、害虫が抵抗性を持つ可能性があります。作用の異なる他の薬剤と交互に使用する「ローテーション散布」を心がけることが、長く効果的に農薬を使うためのコツです。
まとめ:てんとう虫に似た害虫の早期対策


てんとう虫に似た虫への対処は、その虫が益虫か害虫かを正しく見極めることから始まります。特に農作物に被害を与える害虫については、被害が拡大する前の早期対策が収穫量を守る上で極めて重要です。
- てんとう虫の益虫と害虫を見分ける最大のポイントは体の光沢の有無
- 益虫は体がツヤツヤしており、害虫は光沢がなくマットな質感をしている
- 光沢のないオレンジ色の「テントウムシダマシ」はナス科作物の大敵
- テントウムシダマシは葉を網目状に食害し、収穫量に影響を与える
- オレンジと黒の模様を持つ「ナガメ」はてんとう虫に似たカメムシの一種
- 害虫であるテントウムシダマシに人体へ有害な毒はない
- 家の中で見かける茶色いまだら模様の虫はヒメマルカツオブシムシの可能性
- ヒメマルカツオブシムシの幼虫は衣類や乾物を食害する
- 害虫対策の基本は、卵や幼虫のうちに物理的に取り除くこと
- 防虫ネットの使用は、害虫の飛来と産卵を防ぐのに非常に効果的
- 農薬を避けたい場合は、お酢を水で薄めたスプレーが忌避剤として使える
- お酢スプレーは濃度が濃すぎると薬害の原因になるため注意が必要
- 化学農薬のスミチオンは持続性、マラソンは速効性に優れる特徴がある
- 農薬を使用する際は必ずラベルを確認し、用法用量を厳守する
- 日頃から作物の葉の裏などをこまめに観察する習慣が早期発見につながる

高品質な種苗を、ありえない価格で。
中間マージンを徹底的に削減し
\特別価格で販売する種苗通販サイト/





